デジタル通貨・仮想通貨・電子マネーの違いは?中央銀行はデジタル通貨発行へ踏み切るのか
キャッシュレス化が進み、クレジットカードや電子マネーでの支払いがだいぶ浸透してきましたが、ここにきて中央銀行がデジタル通貨を発行するということで、新たな話題になっています。
電子マネーや仮想通貨とは、デジタル通貨とは違いは何なのでしょうか。
どんな人にもわかりやすく読んでもらえるように書いてみたので、ぜひ参考にしてみてください。
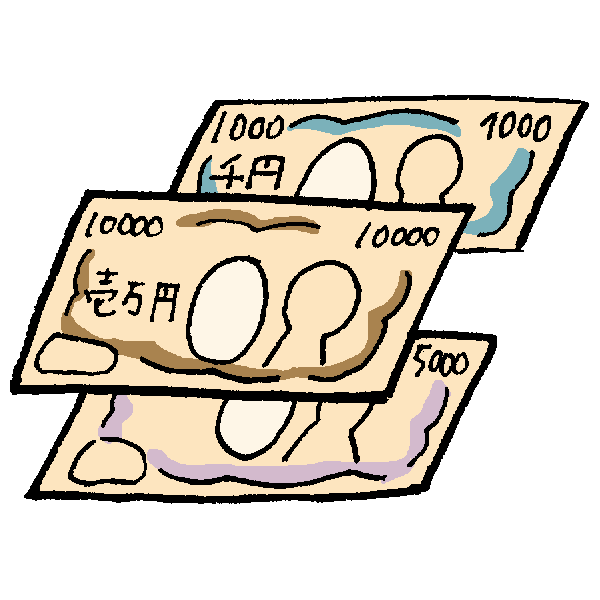
デジタル通貨とは
デジタル通貨とは、現金ではなく、 電子マネー、仮想通貨など「デジタルデータでの通貨」ということになります。
ビットコインなどの仮想通貨も含まれますし、交通系の電子マネーや、paypay、nanacoなどの電子マネーも含まれます。

電子マネーとは
電子マネーは「法定通貨」、つまり円やドルなどをデジタル化したものです。
例えば交通系のSuicaやPASMO。他にもお店がオリジナルで作っている楽天 Edy や nanaco や WAON などがこれにあたります。
Suica や PASMO を使っていても単位は円ですよね。
1000円チャージ、1万円チャージなど、通貨の単位は円です。コンビニなどでも円をカードにチャージしたり、カードで300円だったり1,200円だったりと、買い物をしたりしますよね。硬貨や紙幣を使うのと、まったく変わりはありません。

仮想通貨とは
仮想通貨とは電子マネーとは異なります。
決定的にわかりやすい違いは単位。
例えばビットコインを買うと、ビットコインの単位は円ではなく、単位は1ビットコインということになります。
これが今流通しているわけですね。
しかもこうした仮想通貨とは 国家に依存していない「非中央集権的な通貨」と言われます。
どういうことかと言うと、例えば円は日本国が作っていますよね。アメリカドルはアメリカという国が発行しています。そして、 ユーロは1カ国ではないですが数ヶ国まとまったEU(ヨーロッパ連合)が発行しています。
このように、1つの国や、数カ国の連合などが作り出し、そこから発行されている通貨、国の中央銀行が発行している通貨。
これが従来の通貨です。
しかし仮想通貨は、デジタルデータ上の通貨である上に、国が発行しているものではありません。
仮想通貨は、基本的には国家や組織の管理を受けない特殊な通貨で、その価値は需要と供給のバランスによって決まると言われています。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク中央銀行がデジタル通貨を発行する?
さて、中央銀行がデジタル通貨を発行するということですが、これはどういうことでしょうか。
中央銀行は、お札や硬貨を発行しています。
一円、五円、十円、五十円、百円、五百円、千円、二千円、五千円、一万円とありますが、これらお金の正式名称は「銀行券」と言われます。
これらの銀行券硬貨やお札は誰でも一年365日、24時間使えるものです。
今回の話は、この慣れ親しんだ決済手段「銀行券」をデジタル化してはどうだろうか、ということがニュースになっているのです。
日銀だけではなく、全部で6つの中央銀行の総裁が集まり、デジタル通貨にするかどうかということについて4月に会合をすることになっています。
6つの銀行組織とは、以下の通り。
・日本銀行
・BOE(イングランド銀行。英国。)
・BIS(国際決済銀行。60か国の国・地域の中央銀行が加盟する組織)
・欧州中央銀行(ECB)
・スイス国民銀行
・リクスバンク(スウェーデン中央銀行)
・カナダ銀行
これらの大きな動きが注目されています。

まとめ
今後の貨幣事情がどう移り変わっていくのか、この流れは見逃せません。今後も注目していきましょう。


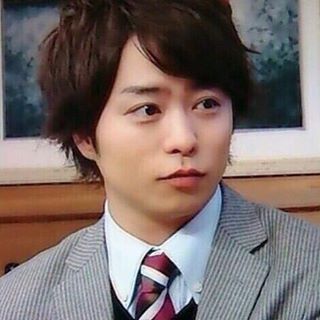
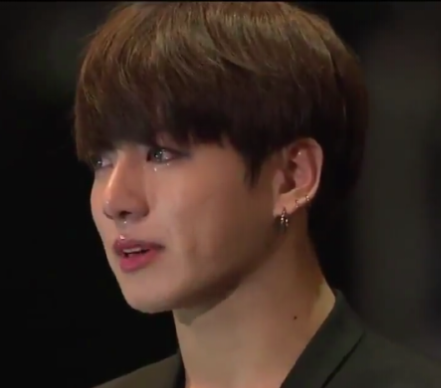
コメント